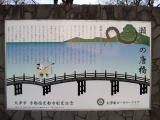第126話 『比叡山周遊』 (滋賀県/大津〜滋賀県/草津 2010年12月5日)





琵琶湖に朝日が登る〜〜♪
琵琶湖大橋から日が出て良い感じです。


準備が整ったので出発〜 向かう先は“京都〜大原♪ 三千院〜♪”
拝観時間まで30分くらいあるので、ゆっくりと散策しながら歩きました。。



↑今年一番の冷え込みで霜が降っていた((=_=))ブルッ
kon
このポスター↓見たら
三千院へ行くたくなる〜^^
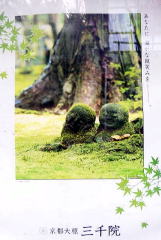



三千院は、妙法院・青蓮院・曼殊院・毘沙門堂とともに天台宗五箇室門跡
のひとつで、最澄(伝教大師)が比叡山に庵を結んだ時、東棟南谷に一堂
を建立したのが起こり。
開門しました〜^^ 「三千院」へ入ります。
拝観入口から客殿へ向かいます。




これぞ求めていた和の雰囲気です↓
←もみじ守り
買いました。



←往生極楽院を過ぎると、
わらべ地蔵が笑顔でお出向かえしてくれます。



苔の絨毯に転がってる感じが
凄くかわいい♪ 癒される〜♪

金色不動堂へ行くと休憩所で“金粉入り梅こぶ茶”を
ふるまっていました。まあ、“美味しかったら買ってね”
という事ですけどね…


もちろん
美味しかったです→
1時間ちょっと院内を廻って外へ出ると、門前のお店も開店していました〜☆ヽ(▽⌒*)♪




←京美茶屋さんで、京名物“にしんそば”と
“ゆばそば”を頂きました。
次ぎは「比叡山延暦寺」へ移動〜〜

比叡山は、高野山と並ぶ日本仏教における聖地で、伝教大師“最澄”が
開山して1200年経ち、比叡山は多くの名僧を輩出したことにより、日本
仏教の母山と呼ばれています。比叡山は大きく三塔(東塔・西塔・横川)
の地域に分けられ、これらを総称して「比叡山延暦寺」といいます。
最澄は天台宗の開祖ですが、浄土宗の法然・浄土真宗の親鸞・臨済宗
の栄西・曹洞宗の道元・日蓮宗の日蓮などが、若き日に比叡山で修行し
ています。



東塔地域には、比叡山延暦寺の総本堂根本中堂
があり、1200年間守り継がれた「不滅の法灯」が
光り輝いています。
↑根本中堂(国宝)
↑お坊さん達も記念写真


←大講堂
比叡山で修行した各宗派の
宗祖の木像が安置されてい
ます。
↓文殊楼
↓鐘楼
○西塔地域

←天台建築様式の代表
とされる釈迦堂


「弁慶のにない堂」
と呼ばれる
常行堂と法華堂→
○横川地域


↑朱塗りの美しい舞台造りが復元された横川中堂


元三大師堂↓

←比叡山ドライブウェイから望む
大津市街地と琵琶湖
比叡山を出発します〜

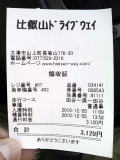
←伝教大師(最澄)尊像
比叡山ドライブウェイって
むちゃくちゃ高い!
3,120円もしたよ(T▽T;) 〜ん!
次ぎは「三井寺」へ移動〜〜

三井寺は正式には園城寺と称し、創建以来1300年の歴史と数々の史実
や伝説に満ちあふれた巨刹です。平安時代には四箇大寺(東大寺・興福寺
・延暦寺・園城寺)の1つに数えられ、現在も山岳寺院として長等山山腹に
広大な境内地を有しています。


←仁王門
慶長6年(1601年)、徳川
家康により甲賀の常楽寺よ
り移築。
釈迦堂→

←金堂への階段下
もみじが美しい〜♪

金堂(国宝)→
当時の総本堂で、豊臣秀吉の
北政所により慶長4年(1599
年)に再建された。
三井の晩鐘↓
この鐘は、音の三井寺として日本三銘鐘のひとつ
にも数えられ、また平成8年7月には環境丁より
「日本の音風景百選」にも認定されています。



↓もう1つの名物鐘、霊鐘・弁慶の引き摺り鐘
弁慶の汁鍋→
その昔、三井寺が比叡山と争ったとき、比叡の荒法師・武蔵坊
弁慶が三井寺に攻め入り、この鐘を奪って比叡山の山頂まで
引き摺り上げて撞いてみると、「イノー、イノー」(帰りたい)と響
いたので、「そんなに三井寺へ帰りたいのか」と谷底へ投げ落
としたといいます。その時のものと思われる引き摺った疵痕や
ヒビがいまも残っています。

↑唐院の三重塔と潅頂塔

↑微妙寺

↑毘沙門堂

↑水観寺
観音堂周辺は紅葉絶好調で〜す♪




↓観音堂、上からの風景も♪↓

←そろばんの碑、発見!
大津は、そろばんの産地です。
お腹空いた…
買ったのは“鮒すし”…珍味だ…お酒飲みたくなったよ…

そして、「瀬田の唐橋」へ寄って…